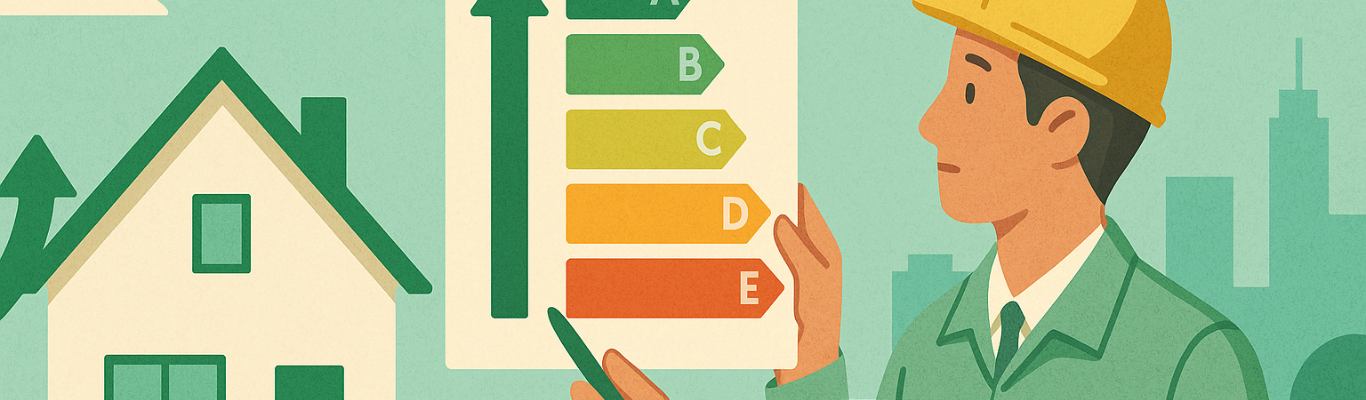2025年の義務化目前!省エネルギー基準の全知識と実践ガイド
省エネルギー基準とは?基本を押さえよう

更新日:2025年10月15日
企業の建築計画や設備投資において、省エネルギー対策は重要な経営課題の一つです。特に、2025年の省エネルギー基準の義務化を控え、オフィスビルや工場、商業施設などの新築・改修において、省エネルギー基準の適合が求められるようになります。
本記事では、企業が遵守すべき省エネルギー基準の概要、背景、建築物省エネ法との関係、適用範囲について解説し、今後の対応に向けたポイントを整理します。
省エネルギー基準の目的と背景
省エネルギー基準は、企業活動におけるエネルギー使用の効率化を促進し、温室効果ガスの排出削減やエネルギーコストの最適化を目的として定められた規制です。近年、カーボンニュートラルの実現に向けた国際的な動きが加速する中で、日本政府もエネルギー消費の削減、脱炭素化の推進、企業の環境負荷低減を強く求めています。
企業の建築物におけるエネルギー消費性能は、「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」によって規定されています。この法律は、建築物の省エネ性能を向上させることを目的とした法規制であり、オフィス、工場、商業施設、病院、学校など、幅広い用途の建築物が対象となります。2025年4月以降は、すべての新築建築物(小規模建築物を含む)に対して、省エネルギー基準の適合が義務化されます。特に、一定規模以上の非住宅建築物については、省エネ基準の適合義務に加えて、省エネ性能を可視化するための「省エネ性能表示制度(BELS)」の活用が推奨されています。
省エネ基準の適合には、建築物の一次エネルギー消費量や外皮性能(断熱・気密)の算定基準を満たすことが求められます。そのため、企業が新築や改修をおこなう際には、設計段階から省エネルギー基準を考慮し、適合する計画を立てることが不可欠となります。今回の改正により、これまで義務化の対象となっていた大規模建築物に限らず、2025年以降は中小規模の建築物や住宅にも適用範囲が拡大されます。その結果、省エネ性能が不十分な建築物の新築や販売が難しくなるため、企業の建築計画にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。
このように、建築物省エネ法と省エネ基準は密接に関係しており、企業が新たにオフィスや商業施設を建設する際には、法規制を遵守しながら、省エネ性能の確保を前提とした設計や施工をおこなう必要があります。
省エネ基準と建築物省エネ法の関係
省エネ法は、建物におけるエネルギー消費の削減を法的に推進する枠組みであり、その具体的な性能水準を定めているのが省エネ基準です。つまり、省エネ基準は建築物省エネ法の実効性を支える技術的な根拠として位置づけられています。企業が新築・改修をおこなう際、建築物省エネ法によって省エネ性能の確保が義務づけられ、その達成手段として、省エネ基準に適合した設計・設備選定が求められます。この基準では、建物の断熱性能や設備機器のエネルギー効率などが定量的に評価され、法令で定められた指標に基づいて適否が判断されます。
省エネ基準の内容は技術革新や社会情勢の変化に合わせて随時見直されており、建築物省エネ法に基づく規制内容もその変化を反映して強化される傾向にあります。企業にとっては、単に法律を守るという姿勢にとどまらず、法と基準の双方を正しく理解し、先を見据えた建築戦略を立てることが、持続的な経営に不可欠となります。
適用範囲と対象建築物
2025年の省エネ基準義務化に伴い、新築・改修における適用範囲が大きく拡大します。企業が関わる建築物の種類によって、適合義務の内容が異なるため、事前に確認が必要です。
対象となる建築物
①オフィスビル・商業施設(店舗・ホテル)
・省エネ基準を満たす外皮性能(断熱性・遮熱性)の確保が必須。
・高効率照明、空調設備の導入によるエネルギー消費削減が求められる。
②工場・倉庫・物流施設
・工場や倉庫におけるエネルギー使用量が大きいため、省エネ設備(高効率ボイラー、LED照明、断熱パネルなど)の導入が重要。
・省エネルギー管理システム(BEMS)の活用が推奨される。
③教育・医療施設(学校・病院)
・冷暖房負荷の削減のため、高性能ガラスや高断熱構造の採用が必要。
・エネルギー消費量の可視化による管理(HEMS・BEMS)の導入が推奨される。
④中小規模の事業用建築物(店舗・小規模オフィス)
・これまでは努力義務だったが、2025年以降は適合義務が発生。
・設計段階から省エネ性能を確保し、エネルギー消費量を抑える対策が必須。
2025年の省エネ基準義務化とは?最新動向を解説

2025年4月より、すべての新築建築物に対して省エネルギー基準の適合が義務化されます。これにより、住宅のみならずオフィスビル・商業施設・工場・病院・学校など、企業が所有・利用する建築物も広範囲にわたり省エネ性能を確保する必要があります。
この改正は、エネルギーコストの最適化やESG経営の推進に大きく関わるため、企業にとって今後の事業計画や建築戦略に影響を与える重要な施策となります。2025年の省エネ基準義務化のポイントや適用範囲、企業が取るべき対応について詳しく解説します。
2025年の改正ポイントと義務化の影響
これまで、省エネルギー基準の適合義務は一定規模以上の建築物に限定されていましたが、2025年の法改正により、すべての新築建築物が対象となります。これにより、企業が所有・利用する建築物にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。
まず、省エネ基準適合義務の対象がすべての建築物へと拡大されます。これまで義務化の対象外であった小規模オフィスや店舗、賃貸物件も適用範囲に含まれるようになり、適合義務を満たさない建築物は新築や増改築が制限される可能性があります。次に、エネルギー消費性能の評価基準が厳格化されます。冷暖房、換気、照明、給湯などの一次エネルギー消費量の削減が求められ、建築物の外皮性能(断熱性・遮熱性)の向上が不可欠となります。また、省エネ性能を数値化・可視化し、第三者による評価を受ける仕組みも強化される見込みです。
さらに、省エネ基準への適合義務を守らなかった場合のペナルティも強化されます。基準を満たさない建築物については、建築許可が下りない可能性があり、事業者やオーナーに対する指導や改善命令の対象となることも考えられます。加えて、ESG経営や脱炭素経営への影響も大きくなります。企業の省エネ対策がESG(環境・社会・ガバナンス)評価に影響を与えるだけでなく、金融機関の融資条件にも関わるようになります。省エネ基準に適合しない建築物は、資産価値が低下するリスクがあるため、企業の建築計画や投資判断において、省エネ対策は不可欠な要素となります。
このように、2025年の省エネ基準義務化は、企業の事業活動や投資判断に直結する重要な改正であるため、早めの準備が必要です。
義務化される建築物の範囲
2025年の改正により、規模を問わずすべての新築建築物が省エネルギー基準の適合義務対象となります。これにより、オフィスや商業施設、工場、倉庫、教育施設、医療施設、住宅、ホテルなど、あらゆる種類の建築物が対象となります。オフィスビルや商業施設、工場、倉庫といった事業用建築物は、これまで一定規模以上のものが対象とされていましたが、2025年の改正によって小規模な店舗や倉庫も適用範囲に含まれることになります。これにより、電力消費の最適化が求められ、省エネ性能の確保が経営戦略の一環としてますます重要になります。
学校や病院、福祉施設といった教育・医療関連の建築物も、省エネ基準の対象となります。特に、公共性の高い建築物ほど、省エネ性能の水準が高く求められます。運営コストの削減を目的とした省エネ対策が不可欠となり、高断熱化や高効率設備の導入が必要となります。
賃貸住宅やマンション、ホテルなどの宿泊施設も適用対象となります。省エネ性能が不十分な物件は、今後、入居率の低下や資産価値の減少といったリスクが高まるため、早めの対応が求められます。特に、新築物件においては、省エネ基準の適合が義務となるため、住宅市場においても省エネ性能の差が競争力に直結するようになります。
さらに、既存建築物の増改築や改修においても、一定規模以上の工事をおこなう場合には、省エネ基準の適用が求められる可能性が高くなります。そのため、企業が所有する建築物の改修計画を立てる際には、省エネ基準を考慮し、補助金制度や税制優遇を活用しながら計画的に進めることが重要になります。
省エネ基準適合義務化に向けた準備
2025年の義務化に向けて、企業が取るべき具体的な準備として、まず省エネ基準に適合した設計や設備の導入が必要になります。設計段階から省エネ基準の適合を確認し、高性能断熱材や高効率窓ガラスを採用することで、断熱性能の向上を図ることが求められます。また、高効率な空調や給湯設備の導入、LED照明やセンサー制御によるエネルギー管理をおこなうことで、建物全体のエネルギー消費を最適化できます。さらに、太陽光発電や蓄電池の導入など、再生可能エネルギーの活用を検討し、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギービル)を目指すことも選択肢の一つとなります。
次に、エネルギーマネジメントシステムの導入も重要な対策となります。BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を活用することで、ビル全体のエネルギー使用量を可視化し、最適な運用をおこなう仕組みを整えることができます。エネルギー消費量のデータ管理と分析を行い、電力・ガス・水道の使用状況をモニタリングしながら削減計画を策定することで、より効率的なエネルギー管理が可能になります。
補助金や税制優遇制度を活用することも、省エネ基準に適合するための重要な手段となります。国や自治体が提供する支援制度を活用し、省エネ改修や高性能設備の導入に対する補助金を受けることで、導入コストを抑えることができます。また、低金利の省エネ住宅ローン(フラット35Sなど)を利用することで、資金調達の負担を軽減できます。加えて、CO₂排出削減に関する優遇措置やカーボンクレジットの活用による税制優遇を受けることで、企業の環境負荷を低減しつつ、財務面のメリットも享受できる可能性があります。
このように、2025年の省エネ基準義務化に向けた企業の準備には、設計・設備の最適化、エネルギーマネジメントの導入、補助金や税制優遇の活用といった多角的なアプローチが求められます。これらの施策を計画的に進めることで、企業の省エネ対策を強化し、持続可能な経営の実現につなげることができます。
省エネ基準適合のポイント

2025年4月からの省エネルギー基準適合義務化により、すべての新築建築物が適用対象となります。企業がオフィスビル、商業施設、工場、倉庫などの新築・改修をおこなう際には、省エネ基準を満たす設計・施工が不可欠となります。
今回、企業の建築計画やプロジェクト推進担当者向けに、省エネ基準適合のためのチェックリストを整理しました。設計、施工、専門家の活用など、各段階での重要なポイントを明確にし、円滑な基準適合を実現するための指針を提供します。
建築・設計時に確認すべきポイント
建築設計の段階で、省エネ基準を満たすかどうかが決定されます。そのため、計画初期から基準適合を意識した設計をおこなうことで、スムーズに適合基準を満たすことが可能になります。
まず、一次エネルギー消費量の最適化が求められます。省エネ基準に基づいた一次エネルギー消費量の計算を実施し、設計段階で適合性を確認することが重要です。また、高効率設備の導入計画を立案し、LED照明や高性能空調、ヒートポンプ給湯器などの採用によってエネルギー使用量を削減することが必要になります。次に、外皮性能の確保も重要なポイントとなります。高性能断熱材を使用することで、屋根、壁、床の断熱性能を向上させるとともに、Low-Eガラスや二重サッシなどの高効率窓・ガラスを採用することでエネルギーロスを抑制します。
このように、建築設計の初期段階で省エネ基準に適合した計画を立てることで、エネルギー効率の高い建築物を実現し、長期的なコスト削減や環境負荷の低減を図ることができます。
施工時の注意点と基準適合の確認方法
設計通りに施工が行われなければ、省エネ基準適合の要件を満たせません。施工管理の精度を高め、適切な品質チェックを実施することが重要です。
断熱・気密施工の適正管理は、省エネ基準に適合する建築物を実現するうえで重要なポイントとなります。施工の際には、断熱材の適切な設置が求められます。設計通りの厚みと密度を確保し、隙間なく施工されているかを確認することが必要です。特に、外壁、屋根、床下の断熱材が適切に配置されているかを現場でチェックし、断熱効果が最大限に発揮されるように管理することが重要です。
施工記録と省エネ性能評価の実施も、品質管理の一環として欠かせません。施工品質を確保するためには、第三者検査の導入が有効です。省エネ性能評価の専門家による監査を実施し、必要に応じてエネルギー消費量や外皮性能に関するデータを提供することで、適合性を証明することができます。
このように、断熱・気密施工の適正管理から設備機器の設置、エネルギー消費量の測定、第三者検査の導入まで、施工の各段階で慎重な管理をおこなうことが、省エネ基準に適合した建築物を実現するための鍵となります。
省エネ基準適合のための専門家相談の活用方法
企業が省エネ基準に適合するためには、専門家のサポートを受けることで、認証取得のプロセスをスムーズに進めることができるだけでなく、施工品質の向上にもつながります。省エネ基準を満たすためには、設計から施工、運用までの各段階で適切な対策を講じることが求められます。
設計段階では、省エネ設計コンサルタントを活用することで、建築計画の初期段階から適切なアドバイスを受けることが可能です。専門家によるエネルギーシミュレーションを実施し、最適な設備の選定をおこなうことで、設計時点での省エネ基準適合を確実なものとすることができます。また、建築物の用途や立地条件に応じた省エネ対策の提案を受けることで、より効果的な省エネ性能の向上が期待できます。
エネルギーマネジメントにおいても、専門家の活用が重要です。BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)やHEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の導入時には、専門家と連携して適切なシステム設計をおこなうことが求められます。これにより、エネルギー使用状況のデータ化や運用の最適化が可能となり、効率的なエネルギー管理を実現することができます。
このように、専門家の活用を通じて、省エネ基準適合に向けた設計・施工・運用を総合的に支援してもらうことで、企業は省エネ対策の効果を最大化し、持続可能な建築計画を実現することができます。
企業のための省エネ基準対応戦略

企業にとって、省エネルギー基準への適合は単なる規制対応ではなく、コスト削減や企業価値向上の観点からも戦略的に取り組むべき重要な課題です。2025年の省エネ基準義務化に伴い、オフィスビル、商業施設、工場など幅広い建築物が適用対象となり、エネルギー消費の最適化が求められています。さらに、企業のESG経営の一環として、省エネ対策は環境への配慮だけでなく、投資家や取引先からの評価を高める要素にもなります。
企業が省エネ基準を満たすためにどのようなコスト最適化戦略を採るべきか、ESG経営との関係、そして導入すべきエネルギー管理ツールについて詳しく解説します。
省エネ基準を満たすためのコスト最適化戦略
企業が省エネ基準をクリアするためには、コストを抑えつつ効果的な対策を講じる必要があります。まず、初期投資を抑えるためには、補助金や助成金の活用が不可欠です。国や自治体は、省エネ基準適合を促進するために、断熱改修、高効率空調設備の導入、再生可能エネルギーの活用などに対して支援策を提供しています。企業はこれらを積極的に活用することで、導入コストを大幅に削減できます。
次に、エネルギーコストの最適化には、設備の効率化が重要です。例えば、最新の高効率LED照明、ヒートポンプ式給湯器、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を導入することで、長期的な運用コストの削減が可能となります。特に、BEMSは建物内のエネルギー消費を可視化し、最適な制御をおこなうことで、大幅な省エネ効果を実現します。
さらに、契約電力の見直しも有効な戦略の一つです。使用状況に応じた適切な契約プランを選択することで、不要なコストを削減し、エネルギー使用量の最適化を図ることができます。
省エネ基準とESG経営の関係
近年、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)経営が重視される中で、省エネ基準への適合は企業価値を高める重要な要素となっています。大手企業では、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減が求められ、取引先にも省エネ基準適合を求める動きが強まっています。
また、環境負荷の低減に取り組む企業は、金融機関や投資家からの評価が向上し、ESG投資の対象となる可能性が高まります。ESGスコアの向上は、株価や企業ブランド価値にも影響を与え、長期的な企業成長に寄与する要素となります。
企業が省エネ対策を実施することで、従業員の働く環境も向上します。例えば、高断熱・高気密のオフィスは、室内温度の安定性が向上し、快適な職場環境を提供できます。これにより、従業員の生産性向上や離職率の低下にもつながるため、企業にとってメリットは大きいといえます。
企業が導入すべきエネルギー管理ツール
省エネ基準適合を効率的に進めるためには、適切なエネルギー管理ツールの導入が不可欠です。現在、企業向けにさまざまなエネルギー管理ツールが提供されており、それぞれの特徴を理解し、自社に適したシステムを選定することが重要です。
まず、BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)は、大規模なオフィスビルや商業施設向けに最適なツールです。建物全体のエネルギー消費を監視・分析し、最適な運用をおこなうことで、電力消費の無駄を削減できます。特に、AIを活用した最適制御機能を備えたBEMSは、リアルタイムでのエネルギー調整が可能となり、さらなる省エネ効果が期待できます。また、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)は、小規模オフィスや工場向けに適したツールであり、照明や空調の使用状況を可視化し、省エネ行動を促す機能を備えています。これにより、従業員の省エネ意識向上にもつながります。
さらに、エネルギーデータの分析ツールを活用することで、企業のエネルギー消費の傾向を把握し、より効果的な省エネ対策を策定できます。クラウド型のエネルギーマネジメントシステムを導入することで、複数の拠点を一元管理し、エネルギー消費を最適化することも可能です。
企業が省エネ基準を満たすためには、単なる規制対応ではなく、経営戦略としての視点を持つことが求められます。コスト最適化、ESG経営との連携、エネルギー管理ツールの活用を通じて、持続可能な成長を実現するための取り組みを進めることが重要です。
省エネ基準対応のためのファイナンスと投資

省エネルギー基準への対応は、企業にとって単なる法的義務ではなく、長期的なコスト削減や資産価値向上につながる戦略的な投資といえます。しかし、省エネ設備の導入には初期投資が必要となるため、適切なファイナンス手法を活用しながら計画的に進めることが求められます。企業が持続可能な経営を実現するためには、補助金や助成金の活用、低利融資の利用、ESCO(Energy Service Company)事業の導入、グリーンボンドやサステナビリティリンクローンといった金融手法を組み合わせることが有効です。
また、省エネ設備の導入には、コスト削減効果が期待できる一方で、ROI(投資対効果)を十分に考慮する必要があります。エネルギーコスト削減額や投資回収期間を事前に試算し、最適な投資戦略を立てることが重要です。特に、省エネ基準適合建築は、エネルギー効率の向上だけでなく、企業の信用力向上や資産価値の増加といった副次的なメリットももたらします。これらのポイントを総合的に考慮しながら、最適なファイナンス計画を策定することが、省エネ基準対応の成功の鍵となります。
省エネ設備導入のための資金調達方法
省エネルギー基準に適合するための設備導入は、企業にとって重要な課題ですが、導入コストが高額になりがちであるため、適切な資金調達が不可欠です。まず、国や自治体の補助金や助成金を活用することで、導入コストの負担を軽減できます。例えば、「省エネ促進補助金」や「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギービル)補助金」、「カーボンニュートラル推進補助金」など、多くの支援制度が設けられています。ただし、補助金を受けるためには、エネルギー削減効果の証明や細かな申請手続きが必要になるため、事前の準備が不可欠です。
次に、低利融資制度を活用することで、資金調達コストを抑えながら設備導入を進めることが可能です。環境省や経済産業省が推進する「環境対応型融資」、日本政策金融公庫の「省エネ設備導入向け融資」などは、金利優遇を受けながら資金を調達できる制度として注目されています。さらに、ESCO事業の活用も効果的です。ESCO事業者が省エネ改修を実施し、その後のエネルギーコスト削減分を企業が支払うことで投資を回収する仕組みであり、初期投資を抑えつつ省エネ対策を実施することが可能になります。
加えて、企業の規模や事業内容によっては、グリーンボンドやサステナビリティリンクローンを活用する選択肢もあります。これらは環境に配慮した取り組みを進める企業にとって、長期的な資金調達の手段として有効です。適切な資金調達手法を選択し、事業の成長と持続可能性を両立させることが、省エネ基準適合に向けた重要なステップとなります。
省エネ投資のROI(投資対効果)の考え方
省エネ設備の導入を検討する際には、単なるコスト負担と考えるのではなく、投資としての視点を持つことが重要です。ROI(投資対効果)を評価することで、省エネ設備がどの程度の費用対効果をもたらすのかを明確にすることができます。特に、エネルギーコストの削減額を正確に算出し、どのくらいの期間で投資が回収できるのかを試算することが必要になります。
例えば、高効率空調設備やLED照明を導入することで、年間20~30%の電力消費量削減が期待できるケースがあります。この場合、初期投資額と年間削減額を比較し、投資回収期間を算出することで、企業の財務戦略における省エネ投資の位置づけを明確にすることができます。また、補助金を活用することで、実質的な投資額を減少させ、ROIを向上させることも可能です。
さらに、省エネ設備には定期的なメンテナンスが必要になるため、維持費を考慮したROI計算をおこなうことも重要です。しかし、高性能な設備ほど耐久性が向上し、メンテナンスコストが抑えられる場合もあるため、長期的な視点での評価が求められます。省エネ設備の導入は、短期的なコスト削減だけでなく、企業の競争力向上や環境負荷低減にもつながるため、総合的なメリットを考慮したうえで、最適な投資判断をおこなうことが必要です。
省エネ基準適合建築の資産価値向上のポイント
省エネ基準に適合した建築物は、単にエネルギーコストを削減するだけでなく、長期的な資産価値の向上にも寄与します。特に、不動産市場においては、環境性能の高い建築物の評価が高まっており、省エネ基準を満たしたビルや施設は、テナント誘致や売却時の競争力を高める要素となります。
例えば、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)やCASBEE(建築環境総合性能評価システム)などの環境認証を取得することで、建物のエネルギー効率の高さを第三者が証明し、物件の信頼性を向上させることが可能になります。これにより、企業のブランド価値が向上し、ESG投資家や金融機関からの評価も高まります。さらに、省エネ建築は長期的なコスト削減につながります。エネルギー効率の高い建物は、テナントの光熱費負担を軽減し、入居率の向上につながるだけでなく、維持管理コストの低減にも貢献します。不動産オーナーにとっても、建物の競争力を維持しながら資産価値を向上させる手段として、省エネ基準適合は不可欠な要素となります。
このように、省エネ基準適合建築は、環境負荷の低減だけでなく、企業の財務戦略や不動産市場における優位性を確保するための重要なポイントとなります。省エネ基準への適合は、環境保護と経済的利益を同時に実現し、持続可能な未来へとつながる企業戦略の鍵となります。